
未来のために、いま子どもたちに伝えるべきこと
次代の愛媛を担う子どもたちに、いま世界がどのような問題に直面しているのかを知ってもらい、これからの社会を持続可能でより良いものにするためにはどうすれば良いのかを、愛媛大学SDGs推進室の多彩な講師陣が、SDGs(持続可能な開発目標)17のゴールを達成するために今できる事やすべき事を、子どもと同じ目線で分かりやすく伝えます。
主
催
愛媛・子どもスポーツ推進協議会 国立大学法人 愛媛大学
令和7年度プログラム
※プログラムの内容は、都合により変更になる場合があります。
4月・5月のテーマ
わたしたちがSDGsのためにできること
4月【わたしたちがSDGsのためにできること -Part 1:急いで解決しなければならない世界の問題と民主主義】
世界が緊急に解決しなければならない深刻な問題が3つある。環境問題、貧困、そして、戦争・紛争だ。この講義では、経済学というお金の流れから社会を理解しようとする分析の方法を用いて、それら深刻な問題の解明に従事する講師が、自分の調査の話を交えながら、講義を進める。1回目の講義では、最初に3つの問題に目を向いけ、その後に小学生でも参加可能な2つの解決方法のうちの1つについて、民主主義という仕組みとともに学ぶ。次回は、もう1つの解決方法として消費選択について学ぶ。
4月のオンライン講座を視聴する
5月【「消費で世界を変える!〜選ぶ力が未来をつくる〜」】
この講義では、私たちの社会をより良い方向に変化させるために誰もができる方法としての消費選択について学んでいきます。消費とは、何かを買うことです。世界は、皆が何かを売ったり買ったりすることで成り立っています。日々の消費という私たちの行動の1つ1つが、世界にメッセージを発信しているということを皆さん、知っていましたが? 商品それぞれでメッセージは異なります。それぞれの商品の発信するメッセージを理解して、意識的に商品を選ぶことで、世界を変えることができるのです。ここでは、基礎技術と3つの応用技術、そして応用技術に関して2つの裏技を学びます。
5月のオンライン講座を視聴する

栗田英幸
専門は、経済学を基盤とした環境学、開発学、平和学。資源産業への依存が社会を悪化させる「資源の呪い」現象を明らかにすべく、多くの国や地域でフィールドワークを重ねてきた。コロナ以降は、地域資源の有効活用や地域活性化に焦点を当て、日本の経験を海外の若者たちに伝える研究・活動にも注力する。
離島興居島に移住し、毎日フェリーで大学に通う変わり者
6月・7月のテーマ
昆虫の養殖用のエサとしての利用への挑戦:持続可能な水産養殖を目指して
6月【水産養殖について】
水産養殖は、年々生産量を増し、現在では人類にとってなくてはならない食料生産システムとなっています。しかし、海洋汚染や資源の乱獲等を引き起こすことから、必ずしも地球環境にやさしい、持続可能な食料生産システムとなっていない面も多くあります。今回の講義では、6月に、養殖はどうやって行われているのか?養殖の環境に対する問題点は何なのか?を理解します。7月には、養殖の問題点のうち、特に海洋資源への影響が最も大きい、養殖に使われるエサに注目し、海洋資源負担をかけないエサとは何かを考えます。海洋資源に負荷をかけないエサとして、私たちが注目しているのが、「昆虫」ですが、昆虫をエサとして利用する意味について考えます。
6月のオンライン講座を視聴する
7月【昆虫を魚のエサに!】
水産養殖は、年々生産量を増し、現在では人類にとってなくてはならない食料生産システムとなっています。しかし、海洋汚染や資源の乱獲等を引き起こすことから、必ずしも地球環境にやさしい、持続可能な食料生産システムとなっていない面も多くあります。今回の講義では、養殖の問題点のうち、特に海洋資源への影響が最も大きい、養殖に使われるエサに注目し、海洋資源負担をかけないエサとは何かを考えます。海洋資源に負荷をかけないエサとして、私たちが注目しているのが、「昆虫」ですが、昆虫をエサとして利用する意味について学んでいきます。
7月のオンライン講座を視聴する

三浦猛
北海道大学大学院博士後期課程修了 水産学博士
専門分野:水産動物生理学
魚類の卵形成および精子形成の分子メカニズム、昆虫の魚介類のエサとしての利用、昆虫の持つ機能性物質の単離と動物への作用メカニズムに関する研究を行なっています。
8月・9月のテーマ
ワンヘルスから考える身近な化学物質汚染
8月【ワンヘルスって何?】
ワンヘルスという言葉を聞いたことありますか?「人、動物の健康と環境(生態系)の健全性は相互に密接につながり、強く影響し合う一つのものである」という考え方のことを言います。現在、私たちの住む地球環境には感染症問題、化学物質汚染、健康問題など様々な問題があり、ワンヘルスの概念に基づいて、解決に取り組む必要があります。今月は人獣共通感染症であるマラリアの現状とその対策(蚊帳、DDT使用)を通じて、健康問題と環境汚染のつながりを解説しています。
8月のオンライン講座を視聴する
9月【ヒトとペット動物の健康は室内環境に繋がっている!?】
今月は、ワンヘルスの視点から室内化学物質汚染がヒトやペットの健康に与える影響を解説しています。現代人の生活の約85%を過ごす室内には様々な化学物質が存在しており、人だけでなく、同じく室内で生活するペット動物も室内ダストや餌などを通じて化学物質を取り込んでいます。特にネコは代謝能力が低いことから、高濃度の化学物質が血中から検出されることも。ペット動物を通じた室内環境汚染の実態解明と、研究の展望についても紹介します。
9月のオンライン講座を視聴する
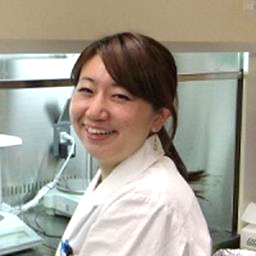
水川葉月
愛媛大学大学院農学研究科
環境計測学研究室
環境化学、環境分析学、環境毒性学を専門とし、野生動物やペット動物に蓄積する化学物質を測定してきた。また、生体内に化学物質が取り込まれた時の代謝反応にも興味を持ち、生物種間でどのように代謝能力が違うのか?その違いが化学物質のリスクに繋がるか?などを研究している。
10月・11月のテーマ
SDGsとAI
10月【AIはSDGsの達成にに役立つの?】
AI(エーアイ)という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。学校でもAIについて学ぶ機会も増えてきました。これからの社会でAIは大きな役割を果たすと言われています。実はSDGsの達成にもAIはとても大きな役割を果たします。今回はAIとはなにかを説明したあと、どのような仕組みで動いているのかをアニメーションを使って説明します。その後、SDGsの達成に役立った例をいくつかご紹介します。
10月のオンライン講座を視聴する
11月【AIはこんなにキケン?】
AIはSDGsの各ゴールを達成するためにもとても強力な助っ人になります。しかし、AIも他の便利なツールと同じように、使い方をあやまるとSDGsのゴール達成は遠のいてしまいます。AIを使う上で知っておきべき危険性をこの回ではしっかり学び、みなさんが将来持続可能な発展にAIを使いこなせるようになってほしいと思っています。
11月のオンライン講座を視聴する
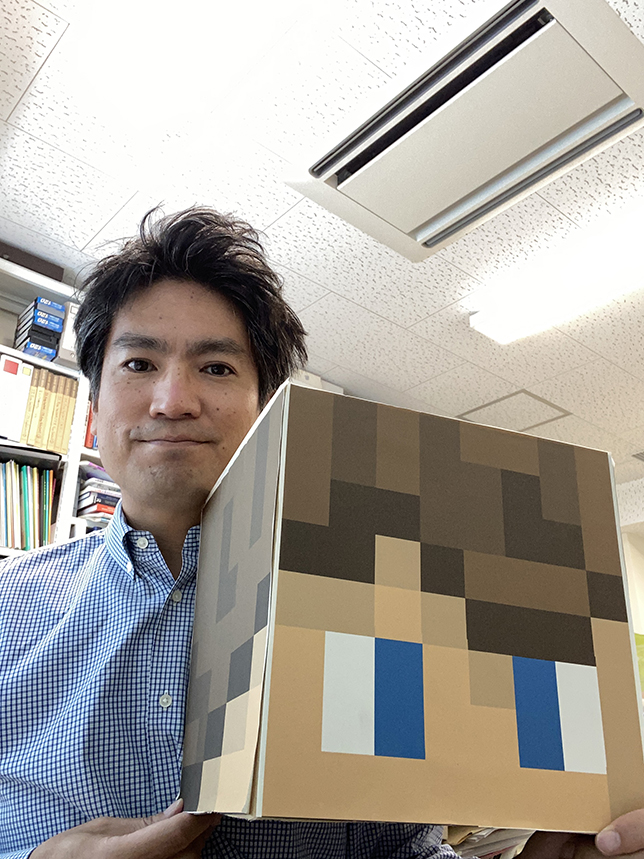
富田英司(1975年/香川県生まれ)
12月・1月のテーマ
自然の力と身近な資源を生かした安心・安全な作物栽培
12月【食べもののごみで野菜を育てる!?ふしぎなコンポスト】
日本の食料自給率は約38%で、多くの食べものは外国から輸入されています。野菜を育てるために大切な窒素・リン酸・カリ肥料の原料も、そのほとんどを輸入に頼っています。そこで、これらの肥料成分を含む食品のごみから作ったコンポストを野菜づくりに活用しました。酸性条件で作る「アシドロコンポスト」をジャガイモ栽培に使い、ほかのコンポストと比べたところ、野菜がよく育ち、雑草の発生も減りました。ごみを資源として生かすことで、肥料や除草剤を減らし、環境や人にやさしい農業につながる事例を紹介します。
12月のオンライン講座を視聴する

浅木直美
愛媛大学農学研究科
土壌肥料学研究室 准教授
作物の生産性向上と環境負荷の低減を両立する栽培技術の開発を目指し、土壌中の養分動態と作物生育との関係について研究しています。
1月【未来の食を守る持続可能な農業】
日本の食糧自給率は約38%と低く、さらに農業者の高齢化や耕作放棄地、化学肥料による水質汚染、農薬使用による生物多様性の低下、地球温暖化ガス発生など多くの問題を抱えています。そのため、持続可能な農業生産が求められており、有機農業が世界的に注目され様々な取り組みが行われています。愛媛大学では「愛媛大学の安心米」という有機栽培で水稲を育て、持続可能な農業を行うための研究開発を行っています。
1月のオンライン講座を視聴する

上野 秀人
国立大学法人 愛媛大学 大学院 農学研究科
食料生産学専攻 農業生産学コース
土壌肥料学教育分野 教授 土壌医
農林水産省で環境に優しい農業研究を行い、その後、愛媛大学でさらに持続可能な農業の研究を進めてきました。家庭菜園を行いたくさんの野菜を栽培しています。とてもおいしい自慢の野菜が収穫できます。
【子どもSDGsニュースVol.1】
SDGsキッズ松山の活動を紹介します!
子どもSDGsニュースは、SDGsの達成のために子ども達が進めるアクションを紹介するシリーズ番組です。第一弾は愛媛大学教育学部の研究室でプラスチックごみのアップサイクルに取り組むSDGsキッズ松山の活動を紹介します。
紹介動画を視聴する
【子どもSDGsニュースVol.2】
SDGsキッズえひめのアップサイクル展始まります!
子どもSDGsニュースは、SDGsの達成のために子ども達が進めるアクションを紹介するシリーズ番組です。第二弾は愛媛大学ミュージアムで開催されるアップサイクル展について紹介します。
紹介動画を視聴する
【子どもSDGsニュースVol.3】
SDGsキッズ高津クラブをご紹介!
子どもSDGsニュースは、SDGsの達成のために子ども達が進めるアクションを紹介するシリーズ番組です。第三弾は新しくSDGsキッズの仲間に加わったSDGsキッズ高津クラブの子どもたちにインタビューしました。
紹介動画を視聴する
